スイッチ保護の決定版!~新FETセットを装着しよう!~
皆様こんにちは! Gunsmithバトンです。
先日発売されました、『FETスイッチデバイス・高効率配線セット』ですが、 『SBD(ショットキー・バリア・ダイオード)』と同様に大好評を頂いております。ありがとうございます^^
従来のFETセットでは複雑な配線の作り直しがありましたが、今回の新FETセットでは既に配線が出来上がっており装着がとても簡単になっているのが特徴です。更に、導線は一般的なものより通電効率の高いものになっていたりコネクターや熱収縮チューブが付属していたりとまさに至れり尽くせりなセットとなっております!
しかし・・・いくら配線が出来上がっていたとしても正しく付けられなければ意味がありません。というわけで、今回はこの『新FETセットの装着の方法や導線の通し方のコツ』を説明していきたいと思います。

1)ハンダごて(一般的な20~30wのもの)
2)こて台
3)ハンダ
4)ニッパー
5)カッター
6)熱収縮チューブ(1.5mm&4mmのもの)
7)電工ペンチ(あると便利)
基本的に用意するものは『ハンダ付け講座』で紹介したものと変わりません。電工ペンチは今回のような端子を装着する加工をする際にあると便利な工具です。詳しくは後ほど説明します。
さあ、作業開始です。今回はスタッフの私物であるLCT製AKMに装着したいと思います。
まずはメカボックスを取り外し、更に元々付いていた導線をハンダごてを用いて外します。ハンダ付けと同じような要領で接合部のハンダを熱して外すのですが、外れにくい場合はこて先に少しハンダを付けておくと熱が伝わりやすくなり簡単に外れます。ちなみに今回はメカボックスを開けずに作業していますが、ハンダ付けやそもそもこういったカスタム等に慣れていない方はキチンとスイッチを取り出して作業しましょう!
次にFETをどこに逃すかを考えます。SBD装着の時と同じようですが、FETの方がデバイスのサイズが大きくより注意が必要です。幸い、AK系のフレームは大きなスペースが多いので簡単に決まりましたが、機種によってはかなりギリギリな場合があります。この逃がしに関しては機種毎に工夫する・・・といった感じですね。今回は前配線(レシーバー内にバッテリーを収める配線)にするので配置はこうなりました。

装着位置が大まかに決まったらスイッチに接合させる『信号線(赤の細い導線)』を適度な長さにカットし、被覆を剥きます。信号線は非常に細いので、カッター等で被覆に切り込みを入れなくても爪で挟んで引っ張れば簡単に剥けます。剥けたら忘れずに予備ハンダしておきましょう!
スイッチ側には導線を外した際に残ったハンダが付いており、これがそのまま予備ハンダとなります。

さあ、いよいよ接合なのですがその前に導線に熱収縮チューブを被せます。付属の熱収縮チューブはこのように4つにカットしておきました。信号線に使うのはこの内の短く等分された方です。残りはモーターコネクターの方に使います。

更に、ここでもう1種類、1.5mm径のチューブを用いて信号線を束ねてあげます。これはなくてもいいのですが、あればキレイに纏まりますし導線の保護にも一役買ってくれます。
全て付けるとこんな感じに。収縮させるのは信号線を接合させてからですので注意!

準備が出来たら接合していきましょう。特にどちらの導線をどちらかにということはありません。各々繋ぎやすい方に接合します。

ここでチューブを収縮させるのですが、接合部と端子の部分をしっかり覆ってあげましょう。こうしないと端子がフレームやメカボックスの側に触れてしまいショートするなど思わぬトラブルを招くことになってしまいます。更に注意点として、下側の端子は少し奥まった部分まで繋がっているという点があります。
銅の端子部分が奥まで繋がっているのがおわかりいただけますでしょうか。ここが見落としがちな部分ですので注意して下さい!

見辛い写真で申し訳ありません(汗) 先程の写真にあった奥まで続く端子をカバーするために、チューブをここまで差し込んで収縮させます。


さて、次はコネクター類の装着なのですが・・・ここでもう一度おおまかな位置関係を確認しましょう。バッテリー側の配線(赤と黒の組み合わせ)はフレームに組み込んでからでないと分からないのですが、モーターに繋ぐ配線(赤と白の組み合わせ)は明らかに長いのがわかると思います。

いつもならここで「長さを調整してカット!」と言いたいところなのですが、その前に今回は1つ手を加えてみようと思います。
それがコチラ!ここで4mm径の収縮チューブを使います。先程の信号線を束ねたのと同様でキレイに纏まり導線も保護できます。

では、配線の長さの調節をしましょう。この時点でもうメカボックスに手を加えるようなことはないので、先にフレームに組み込んでしまいます。ここで気を付けなければならないのは、配線をメカボックスとフレームで噛まないようにすることです。


一番簡単で確実な方法としては、最初の配線を外す前の状態を写真に撮っておき、それの通りに戻すことです。しかし、元の状態よりも無理のない配線が他に考えられる場合もありますので、そこは是非頭を捻ってみましょう!これを考えるのもカスタムの楽しみの1つだと思います。
ちなみに、AK系のモーター側の配線はメーカーにもよりますが固定ストックかフォールディングストックかで配線の通し方が変わります。

対してこちらがフォールディングストックタイプの通し方。フォールディングストックタイプのフレームには、ストック基部に補強の為のパーツが入っていることが多く配線を通せないためこのような通し方になります。

また、これもメーカーによるのですがこの様に配線が通せるような窪みがありますので、これをよく見てどこを通すのが良いかを考えてみましょう。


メカボックスを組み込めたら配線の長さ調整です。あまりきつくせず、適度に余裕のある長さにカットしましょう。

これは『電工ペンチ』といって、導線と端子をかしめて接合できるというすぐれものです!今回のものはかしめ加工しか出来ませんが、種類によってはコードの切断から被覆剥きまでできるものもあります。
使い方は非常に簡単・・・なのですが注意すべきポイントが1つあります。それは端子の爪の向きと電工ペンチの向きです。とはいえ言葉ではなんとも説明しにくいので、写真をご覧になっていただきましょう。
これがモーターコネクターです。そして、注意すべき爪というのが手前側に見えるU字の部分とその隣にある一回り低く幅広な部分。かしめる際には背の高い爪が被覆部分を、低い方が芯線を抱え込む形になるわけです。


電工ペンチの歯が噛み合う部分に小さな突起があるのがおわかりいただけますでしょうか。この部分をコネクターの爪が開いている方に押し付けかしめます。


この通り、しっかりかしめることが出来ました。


さあ、モーター側が完了すれば残すはバッテリー側のみです。今回は前述の通り、前配線でレシーバー内にバッテリーを収めます。使用するバッテリーは『BATON airsoft リポバッテリー7.4v1100mAh[20C](AKうなぎ)』なので、このバッテリーをセッティングして長さを調整しましょう・・・と、思ったのですが今回は調整なしでぴったりでしたのでこのままコネクターを装着します。

因みに、こちら側の配線も4mm径のチューブでしっかりカバーしました。LCT製のAKのボルトにはメカボックスに沿い被さるようなカバーが付いていますので、ボルトを引くとこの部分が配線を傷付ける可能性があります。また、収め方によってはデバイスの被覆にも干渉する場合が考えられますので、無闇にボルトを引かない等の注意が必要です。
また、今回は装着しませんでしたがヒューズを組み込みたいという方は写真で指し示している箇所、この赤の導線の部分に装着して下さい。他の機種の場合も同様にバッテリー側の赤の導線に装着しましょう。

さて、ピンもしっかり電工ペンチでかしめてコネクターを装着してあげれば完成です!
どうでしたか?注意すべき点はかなり多かったですが、それほど難しい作業ではありません。この手軽さでFETを装着できるとあれば見逃す手はありませんよね!
『SBDでもスイッチ保護は申し分なかったけどまだ満足できない・・・』なんて方は是非ともチャレンジしてみてください!

先日発売されました、『FETスイッチデバイス・高効率配線セット』ですが、 『SBD(ショットキー・バリア・ダイオード)』と同様に大好評を頂いております。ありがとうございます^^
従来のFETセットでは複雑な配線の作り直しがありましたが、今回の新FETセットでは既に配線が出来上がっており装着がとても簡単になっているのが特徴です。更に、導線は一般的なものより通電効率の高いものになっていたりコネクターや熱収縮チューブが付属していたりとまさに至れり尽くせりなセットとなっております!
しかし・・・いくら配線が出来上がっていたとしても正しく付けられなければ意味がありません。というわけで、今回はこの『新FETセットの装着の方法や導線の通し方のコツ』を説明していきたいと思います。
~用意するもの~
1)ハンダごて(一般的な20~30wのもの)
2)こて台
3)ハンダ
4)ニッパー
5)カッター
6)熱収縮チューブ(1.5mm&4mmのもの)
7)電工ペンチ(あると便利)
基本的に用意するものは『ハンダ付け講座』で紹介したものと変わりません。電工ペンチは今回のような端子を装着する加工をする際にあると便利な工具です。詳しくは後ほど説明します。
~作業開始!~
さあ、作業開始です。今回はスタッフの私物であるLCT製AKMに装着したいと思います。
まずはメカボックスを取り外し、更に元々付いていた導線をハンダごてを用いて外します。ハンダ付けと同じような要領で接合部のハンダを熱して外すのですが、外れにくい場合はこて先に少しハンダを付けておくと熱が伝わりやすくなり簡単に外れます。ちなみに今回はメカボックスを開けずに作業していますが、ハンダ付けやそもそもこういったカスタム等に慣れていない方はキチンとスイッチを取り出して作業しましょう!
次にFETをどこに逃すかを考えます。SBD装着の時と同じようですが、FETの方がデバイスのサイズが大きくより注意が必要です。幸い、AK系のフレームは大きなスペースが多いので簡単に決まりましたが、機種によってはかなりギリギリな場合があります。この逃がしに関しては機種毎に工夫する・・・といった感じですね。今回は前配線(レシーバー内にバッテリーを収める配線)にするので配置はこうなりました。
装着位置が大まかに決まったらスイッチに接合させる『信号線(赤の細い導線)』を適度な長さにカットし、被覆を剥きます。信号線は非常に細いので、カッター等で被覆に切り込みを入れなくても爪で挟んで引っ張れば簡単に剥けます。剥けたら忘れずに予備ハンダしておきましょう!
スイッチ側には導線を外した際に残ったハンダが付いており、これがそのまま予備ハンダとなります。
さあ、いよいよ接合なのですがその前に導線に熱収縮チューブを被せます。付属の熱収縮チューブはこのように4つにカットしておきました。信号線に使うのはこの内の短く等分された方です。残りはモーターコネクターの方に使います。
更に、ここでもう1種類、1.5mm径のチューブを用いて信号線を束ねてあげます。これはなくてもいいのですが、あればキレイに纏まりますし導線の保護にも一役買ってくれます。
全て付けるとこんな感じに。収縮させるのは信号線を接合させてからですので注意!
準備が出来たら接合していきましょう。特にどちらの導線をどちらかにということはありません。各々繋ぎやすい方に接合します。
ここでチューブを収縮させるのですが、接合部と端子の部分をしっかり覆ってあげましょう。こうしないと端子がフレームやメカボックスの側に触れてしまいショートするなど思わぬトラブルを招くことになってしまいます。更に注意点として、下側の端子は少し奥まった部分まで繋がっているという点があります。
銅の端子部分が奥まで繋がっているのがおわかりいただけますでしょうか。ここが見落としがちな部分ですので注意して下さい!
見辛い写真で申し訳ありません(汗) 先程の写真にあった奥まで続く端子をカバーするために、チューブをここまで差し込んで収縮させます。
これで信号線の接合は完了です!
さて、次はコネクター類の装着なのですが・・・ここでもう一度おおまかな位置関係を確認しましょう。バッテリー側の配線(赤と黒の組み合わせ)はフレームに組み込んでからでないと分からないのですが、モーターに繋ぐ配線(赤と白の組み合わせ)は明らかに長いのがわかると思います。
いつもならここで「長さを調整してカット!」と言いたいところなのですが、その前に今回は1つ手を加えてみようと思います。
それがコチラ!ここで4mm径の収縮チューブを使います。先程の信号線を束ねたのと同様でキレイに纏まり導線も保護できます。
では、配線の長さの調節をしましょう。この時点でもうメカボックスに手を加えるようなことはないので、先にフレームに組み込んでしまいます。ここで気を付けなければならないのは、配線をメカボックスとフレームで噛まないようにすることです。
先ずは信号線。メカボックスの前、ノズルの脇を通す感じですね。
モーター側の配線はこんな感じ。
一番簡単で確実な方法としては、最初の配線を外す前の状態を写真に撮っておき、それの通りに戻すことです。しかし、元の状態よりも無理のない配線が他に考えられる場合もありますので、そこは是非頭を捻ってみましょう!これを考えるのもカスタムの楽しみの1つだと思います。
ちなみに、AK系のモーター側の配線はメーカーにもよりますが固定ストックかフォールディングストックかで配線の通し方が変わります。
こちらが固定ストックタイプの通し方。
対してこちらがフォールディングストックタイプの通し方。フォールディングストックタイプのフレームには、ストック基部に補強の為のパーツが入っていることが多く配線を通せないためこのような通し方になります。
また、これもメーカーによるのですがこの様に配線が通せるような窪みがありますので、これをよく見てどこを通すのが良いかを考えてみましょう。
メカボックスを組み込めたら配線の長さ調整です。あまりきつくせず、適度に余裕のある長さにカットしましょう。
ここでモーターコネクターを取り付けるのですが、今回はこの工具を使います!

これは『電工ペンチ』といって、導線と端子をかしめて接合できるというすぐれものです!今回のものはかしめ加工しか出来ませんが、種類によってはコードの切断から被覆剥きまでできるものもあります。
使い方は非常に簡単・・・なのですが注意すべきポイントが1つあります。それは端子の爪の向きと電工ペンチの向きです。とはいえ言葉ではなんとも説明しにくいので、写真をご覧になっていただきましょう。
これがモーターコネクターです。そして、注意すべき爪というのが手前側に見えるU字の部分とその隣にある一回り低く幅広な部分。かしめる際には背の高い爪が被覆部分を、低い方が芯線を抱え込む形になるわけです。
この爪が開いている方を上向きとして、電工ペンチにはこのようにセッティングします。
電工ペンチの歯が噛み合う部分に小さな突起があるのがおわかりいただけますでしょうか。この部分をコネクターの爪が開いている方に押し付けかしめます。
この通り、しっかりかしめることが出来ました。
さあ、モーター側が完了すれば残すはバッテリー側のみです。今回は前述の通り、前配線でレシーバー内にバッテリーを収めます。使用するバッテリーは『BATON airsoft リポバッテリー7.4v1100mAh[20C](AKうなぎ)』なので、このバッテリーをセッティングして長さを調整しましょう・・・と、思ったのですが今回は調整なしでぴったりでしたのでこのままコネクターを装着します。
因みに、こちら側の配線も4mm径のチューブでしっかりカバーしました。LCT製のAKのボルトにはメカボックスに沿い被さるようなカバーが付いていますので、ボルトを引くとこの部分が配線を傷付ける可能性があります。また、収め方によってはデバイスの被覆にも干渉する場合が考えられますので、無闇にボルトを引かない等の注意が必要です。
また、今回は装着しませんでしたがヒューズを組み込みたいという方は写真で指し示している箇所、この赤の導線の部分に装着して下さい。他の機種の場合も同様にバッテリー側の赤の導線に装着しましょう。
さて、ピンもしっかり電工ペンチでかしめてコネクターを装着してあげれば完成です!
どうでしたか?注意すべき点はかなり多かったですが、それほど難しい作業ではありません。この手軽さでFETを装着できるとあれば見逃す手はありませんよね!
『SBDでもスイッチ保護は申し分なかったけどまだ満足できない・・・』なんて方は是非ともチャレンジしてみてください!
BATON airsoft FETスイッチデバイス・高効率配線セット



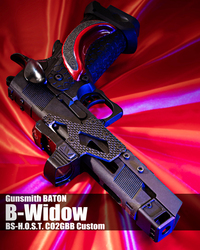

![[ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について [ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について](http://img01.militaryblog.jp/usr/g/u/n/gunsmithbaton/IMG_3490a-s.jpg)

















